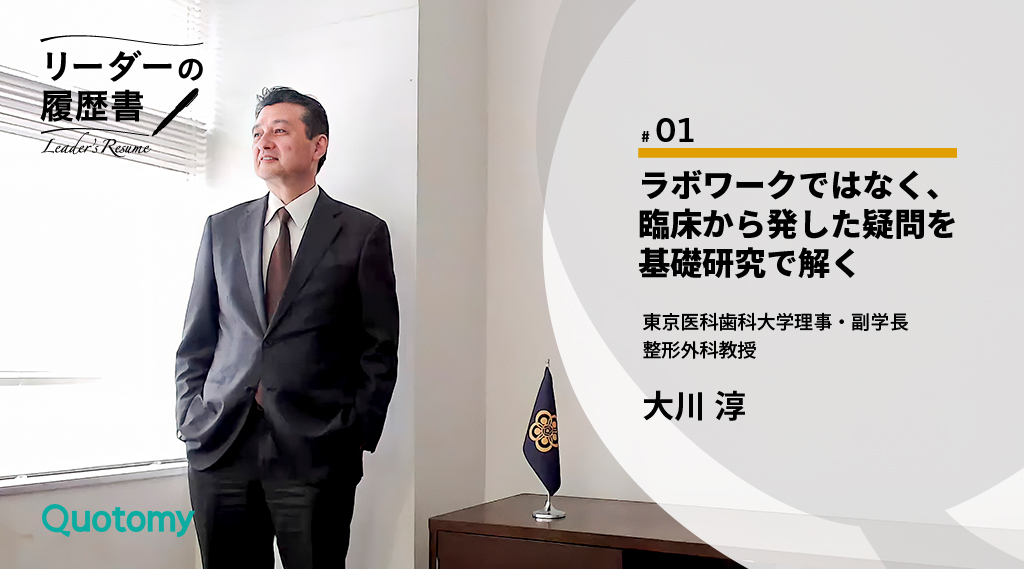
【#01 大川淳先生】ラボワークではなく、臨床から発した疑問を基礎研究で解く
本編に登場する論文
A cadaveric study on the stability of lumbar segment after partial laminotomy and facetectomy with intact posterior ligaments
A Okawa, K Shinomiya, K Takakuda, O Nakai
J Spinal Disord. 1996 Dec;9(6):518-26.
Dynamic motion study of the whole lumbar spine by videofluoroscopy
A Okawa, K Shinomiya, H Komori, T Muneta, Y Arai, O Nakai
Spine (Phila Pa 1976). 1998 Aug 15;23(16):1743-9.
── 大川先生、よろしくお願いします。
まず、先生が医師になって最初に整形外科に進もうと決めた理由を教えてください。
私達の頃は、まだ初期臨床研修制度もない時代ですので、卒業してすぐに各診療科に入局します。
どの診療科に行くか皆迷っていた訳ですけれども、私は学生の時代から脊椎外科をやりたくて整形外科を選んだという感じです。
── 脊椎に何か特別な思い入れがあったのでしょうか?
その頃に神経内科の教室が新設されて、神経に対して興味があったのでしょうね。
けれども、当時の神経内科は文献読んで19〇〇年に報告されたものでは、、、のような話が中心だったので自分の適性として少し違うかなと思いました。
一方で、自分は外科系が向いているだろうと思い、神経に興味があったので脳神経外科と迷ったのですが、当時の整形外科教室には山浦伊裟吉先生という靭帯骨化症の手術を開発した人間がいたので、自分もやってみようと整形外科に入局することになりました。
── 東京医科歯科大学の研修はどんなシステムだったのでしょうか?
最初から脊椎のグループに入ったのですか?
教室会議というシステムがあって、最初の6か月は大学で研修をやって、その後の2年間は一般病院で整形外科を学ぶ、という流れでした。
大宮赤十字病院、国立横須賀病院、中野総合病院などで勤務したのち、脊椎でやっていくには九段坂病院に行く必要があるということで、さきほどの山浦伊裟吉先生がいらっしゃった九段坂病院に行くことになりました。
── 九段坂病院は当時から脊椎のメッカだったのですね。
山浦先生が靭帯骨化症に対する前方除圧固定術を確立されたのですか?
その頃からメッカでしたね。
有名な指揮者の方が頚椎手術を受けに来られたりしていた頃でした。
山浦先生が考案されたのは、むしろ骨化浮上術であって、前方除圧固定に関しては1980年より前にもう存在していたと思います。
まだ頚椎椎弓形成と前方除圧固定のどちらが良い、というエビデンスが確立していない時代でした。
ただ、頚椎椎弓切除で1枚ごとに椎弓を切除すると急激に脊髄が局所的に後方シフトし、残った椎弓と脊髄がkinkingを起こして脊髄損傷を引き起こすというケースがあったわけです。
それに対して広範囲同時除圧の重要性が桐田先生により提唱され、前方からゆっくり骨化を浮上させるっていうコンセプトで山浦先生が1980年頃より骨化浮上術を確立されたそうです。
九段坂病院では、そういう手術を中心にやってきました。
── 現在にも繋がるコンセプトですね。

── 九段坂のあとは、大学に行かれるのでしょうか?
東京医科歯科大学では、ひとりで1回どこか先輩のいないところに行って、修行するって言ったら変ですけれど、手術を自分の判断でやるというシステムだったんですね。
ですので、九段坂病院のあとは横須賀病院で自立して手術をやっていたというわけです。
その後の浴風会では、今回登場するバイオメカニカルな論文を書きました。
当時、九段坂病院で中井修先生が腰部脊柱管狭窄に対して拡大開窓術という術式をご自身で開発されていたのですね。
腰椎の椎間関節の部分切除ですけど、椎弓切除に比べて安定性が高いのではないかという仮説でやっていたのですが、臨床現場では証明できなかった訳です。
バイオメカニカル研究の結果があって術式を開発した、というよりはコンセプトを基に手術を始めておられた。
私としてはバイオメカニカルにどうなんだろうと知りたかったのです。
一番手っ取り早いのは留学してバイオメカニカル研究をするという進路だったと思うのですが、すでに結婚していて子供もいたので、なかなか留学は難しいという判断に至りました。
では、どうしようかって言った時に、浴風会は老人施設なのですけれども、昔から入所条件として解剖があったのですね。
脳神経内科の先生がそういうシステムを作った場所で、解剖率が高い場所だったのです。
わたしは留学ができない中でバイオメカニカル研究をやるためにカダバーが欲しかったので、そこで浴風会に常勤で行くことにしてお願いをして腰椎柱を貰ったのです。
それを大学に持ってきて実験させていただいたということです。
── 凄いです。
御略歴からだけでは読み取れないエピソードですね。
リサーチマインドがあってご自身で積極的にキャリア形成されていると思ったのですが、医局から提案してもらってその進路が決まっていたのでしょうか。
自分でこういう研究をやりたいっていう気持ちがあっただけで、こういう道があるとか誰かにsuggestionいただいた訳ではないですね。
あくまで自分の中で関連病院の中にこういう所があるので、ということで交渉を始めて、最終的に自分で決めて行ったということになります。
── 道を切り拓いていますね。
そこで論文を1本書きあげている点もすごいです。
全然凄くないです、笑
アメリカ行ったら多分半年もあれば書けた論文だと思います。
整形外科医局にバイオメカニカルな研究ができるラボもなかった。
大学に材料と生体力学研究をしている歯学部附属の研究所あって、そこのPhDの先生と御相談しながら手作りでやっていったので、物凄い時間がかかりました。
大学院に行っていなかったので、カダバーをもらう許可を得るために浴風会の常勤にならざるを得なかった。
臨床しながら附属研究所にも通ったので、正直言ってあまり効率の良い研究ではなかったですね。

── また別の研究で1998年にSpineに掲載されている論文があります。
これは大学でやられた臨床がきっかけになっているのでしょうか?
これは今でも議論になる、脊椎の不安定性って何?という話です。
昔、Panjabiという、国際学会の中でも大御所だったインド人のPhDが書いた教科書のClinical Biomechanics of the Spineを読んでみると、腰椎不安定性を「中間位付近での可動性の大きさ」と定義されていたのです。
ちょっとした時にバンっと中間位付近で動く、ということです。
ところが、臨床現場では変性すべり症の患者さんのどういう患者さんに固定術をして、どういう患者さんは除圧術だけでいいのかと術式を判断する時に可動域の大きさがひとつのファクターとして扱われてますよね。
あとは後方開大するかも判断基準にしていたりします。
わたしは、きっとそうではないだろう、と思ったんですね。
バイオメカニカルな考え方からいくと中間付近の動きをdetectしない限りは不安定性というのは本当に理解できないだろうと思ったんですよ。
当時はマッキントッシュの出たての頃。
ビデオレコーディングすることで、そのビデオ画像を静止画にコンバートできるようになった。
それで患者さんの透視画像を取って静止画にして計測した、という論文です。
一秒間の動きを15コマぐらいに切って角度計測をしたんですよ。
ビデオ画像を一生懸命見てると、本当に不安定な人っていうのは動きの真ん中あたりでカクッといく時があるんですよね
そういうものを見つけた、という結果でした。
── とても面白いです!
先生の研究は臨床に即した話が多いですね。
ラボワークではないので、臨床から発した疑問を少しベーシックなものに置き換えたら、こういう理解ができるだろう、、、という方向性でやってましたね。

── その頃に医学博士を取られたのですか?
私は大学院にいっていないので、いわゆる論文博士です。
カダバー集めたり、バイオメカニカル研究をやったりしてできたことで申請しました。
── 他の人が大学院に行く中で、そうじゃない場所で臨床に即した研究をされて、ちゃんと論文を書いて医学博士を論文博士で取るって素晴らしいですね。
いま考えるとすごく無駄、笑。
こういう人が出ないように今はシステム作りをしています。
当時は大学院に行きづらかった問題がいくつかありました。
留学もそうなんですけども、経済的な問題って大きいじゃないですか?
その頃は今と違って、留学にしても大学院にしても自腹を切って研究費を作ってやるしかない時代だった訳です。
私の場合、家庭持ちで子供が少し大きかったので余裕がなく、そこまで踏み切れなかったっていうのが正直なところでした。
今、大学のシステムを自分で作るようになってからは、大学院生の生活は非常に大事だという風に考えています。
今では当たり前なのかもしれませんが、しっかり外勤にも行ってもらいます。
当時の雰囲気は、例えば研究室の消灯時間の話で深夜まで明かりが点いていると評価されるとか、あるいは土日にも研究にいかなければならない、というようなことを上層部が真顔で話していました。
今はちょっと違うかなって思いますね。
── リーダーがそう言ってくださると、ちゃんと安心して研究できる環境になるかと思います。
その後は大学での臨床生活に戻るのでしょうか?
関連病院を維持するために医局員は義務を務めなければいけない。
義務を務めた後は、自分の好きなところに行けるという考え方だったんですね。
その義務の1つに、ある程度の年次でどこかの部長業務をこなすっていうのがあり、長野県の諏訪中央病院のところに医長として赴任しました。
地方の中核的な病院で医長として整形外科という診療科を切り盛りするというのも1つの勉強だったのですね。
当時、「がんばらない」という本を書いた鎌田實先生がずいぶん前に諏訪に行かれていて、そこで地域医療をやっておられたのですね。
佐久総合病院と諏訪中央病院っていうのは長野県の中で地域医療の双璧だったのです。
患者さんに寄り添うという、当時からすると先進的な考え方をもった病院でした。
その後、2001年に大学に戻ってきて普通に整形外科医として働いていましたが、ターニングポイントは初期臨床研修制度が始まる時でした。
#02に続く
こちらの記事は2021年6月にQuotomyで掲載したものの転載です。